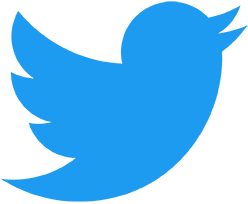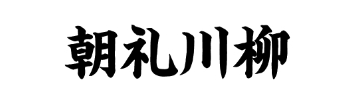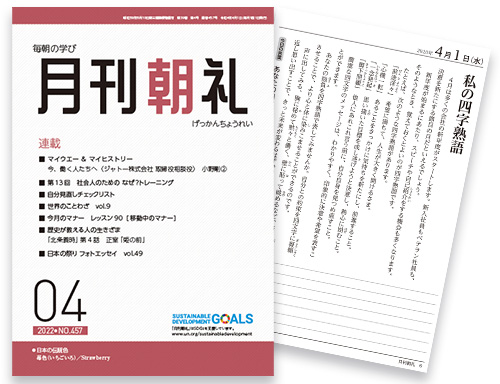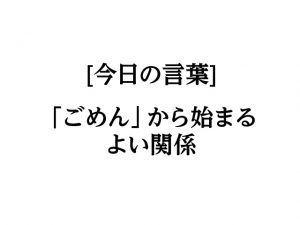
おはようございます。
きょうだいは、同じ家庭環境のなかで育ち、両親の愛情の奪い合いや自己主張のぶつかり合いから、けんかをすることがよくあります。きょうだいげんかからは、相手に対する思いやりの気持ちを学ぶことができます。
教育評論家の尾木直樹さんは、人間関係を学ぶ1つの方法ととらえて、「すぐに止めなくてもいい」と言います。ただし、相手を傷つけるような度が過ぎたけんかは、きっちりと対処すべきと付け加えています。
社内では、
「私には3人の男の子がいます。みんな元気がよく、年が近いので、けんかをすることも多いです。そんななか、上の子は『お兄ちゃんだから』と怒りを抑えたり、『今年はきょうだいげんかをしない』と宣言したりなど、日々成長しているのを感じます。これからも、子どもが多くのことを学べるよう、しっかり親として見守っていきたいと思います」
「幼いころ、弟とよくけんかをしたことを思い出しました。きょうだいげんかを通して、年下を思いやる心や、責任感を身に付けられたと思います。そこから学んだことは、大人になった今も、自分の性格に影響を与えているのは間違いありません。子ども時代に、けんかや仲直りの経験ができたのは、自分にとって良いことだったとあらためて感じました」
「一人っ子の私は、きょうだいげんかをしたことがありません。そのため、両親は私をできるだけ多くの人と触れ合わせる努力をしていました。いとこたちや近所の子どもとけんかをしながら、他人の痛みを知ったり、自分の感情をコントロールしたりすることを覚えていきました。昔より一人っ子の家庭が増えている現在、きょうだいに代わる人間関係が求められています。親同士で協力して子育てするなど、地域での取り組みが必要だと思いました」
という意見が出ました。
「うちの子は、なぜこんなによくきょうだいげんかをするのだろう」
そんなふうに悩む人もいるかもしれません。しかし、子どもにとってきょうだいは、社会性を学ぶ相手でもあります。けんかを通して他人を尊重することを覚え、謝罪する心の大切さや寛容の精神を学ぶのです。きょうだいがいる人なら誰しも、経験があるのではないでしょうか。
きょうだい双方の思いをくみ取って判断し、「けんかにならないためには、どうすればよかったか」を気づかせると、コミュニケーション力が身に付き、子どもが成長するステップになるのです。子ども時代に学ぶ「仲直りの仕方」や「謝罪の仕方」は、大人になったときこそ、人間関係に大きく役立つはずです。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」