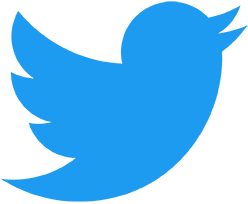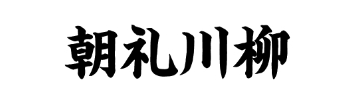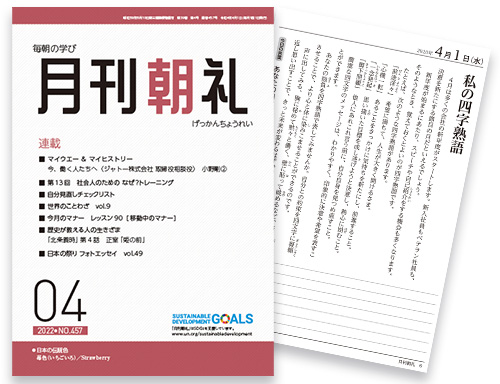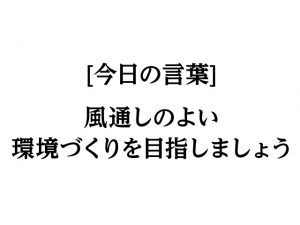
おはようございます。
シリコンバレーには「早く失敗しろ」という有名な言葉があります。時間と費用を使い過ぎる前にあらゆることを検討し、失敗して学んだことが成功につながるという意味です。もちろん、高い目標に挑戦することが前提です。
しかし、日本では失敗が大切ということがわかっていても、多くの企業ではまだ失敗しにくい環境のままです。そのため、社員は失敗する気になりません。
失敗を恐れないことも、それを評価することも難しいことです。しかし、失敗してもよい、という雰囲気をつくることは、職場に新しい風を吹かせるために必要な課題なのです。
社内では、
「失敗を隠すと同じ失敗をくり返すことになり、企業にとってよい結果をもたらしません。失敗し、それを公表して共有することで、会社の体制が整えられ、新しいものが生み出せるようになると思います」
「失敗は成功のもとと言われますか、日本の会社は、まだ失敗しづらい環境だと実感しています。失敗から学ぶよりも、初めから失敗しないようにと石橋を叩かせる風潮があります。しかし、無難な結果よりも、攻めて失敗をする方が、後の成長につながります。後輩が失敗し、そこから何かを学びやすい雰囲気を作れるように努力したいです」
「私は新入社員のころ、たくさんの失敗をしました。早い段階で失敗すると、経験が蓄積され、先手を打つことができるようになります。それは、後輩や部下を教育するための強い原動力になるはずです。いつでも後輩の失敗をフォローできるようにしておくつもりです」
という意見が出ました。
グーグルの研究機関であるグーグルXの統括責任者、アストロ・テラーさんは失敗を推奨しています。失敗した社員をみんなの前で評価します。失敗できる雰囲気を作るようにすると、会議で積極的に新しいアイデアが出されるようになりました。社員や部下を押さえ付けるのではなく、失敗してもそこから何かを見つけ出せばよいという環境を作ると、社員は積極的に仕事に取り組み、失敗から成功のもとを発見するはずです。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」