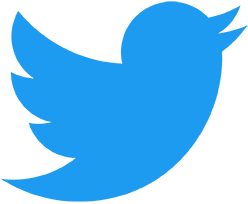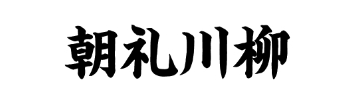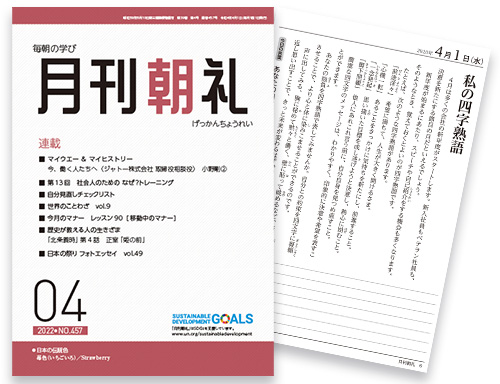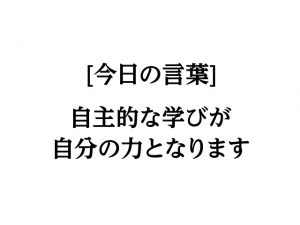
おはようございます。
宮大工として数多くの建築を手掛ける小川光夫さんは、21歳のときに法隆寺の宮大工棟梁である西岡常一さんに弟子入りしました。西岡さんには、「教わったものは自分じゃない。教えるのは一見親切に見えるが、結局は身に付かない」という考えがあったため、現場でも指導をしてもらえなかったそうです。そこで小川さんは、西岡さんの仕事を見て、道具の使い方、大工としての勘、立ち居振る舞いなどを必死に覚えていきました。
社内では、
「学ぶの語源は『まねぶ』だと聞いたことがあります。人から学ぶ場合は、全てを教えてもらうのではなく、まねて身に付けていくことが大切だと、あらためて知りました。上司や先輩のよい点を自分なりにまねながら、成長していきたいと思います」
「人の知識を盗む前に、まず自分に何が足りないかということに気づき、感じる力が必要です。それがわからなければ、誰から何を盗めばよいか判断ができません。それがわかれば、あらゆることに関心を持ち、意欲的に取り組めるはずです」
「学校でパソコン操作などの一般的な知識は学びましたが、仕事を始めるとソフトの使い方やデータのまとめ方など一から教わることばかりでした。仕事をしながら、技術だけを覚えてもそれだけでは一人前になれないこともわかってきました。コツや勘などは、先輩の仕事を手伝う中で身に付くことも多かったので、これからも貪欲にそれらを盗んでいきます」
という意見が出ました。
小川さんは西岡さんから渡された、透けるほど薄いかんなくずを壁に貼り、同じようなかんなくずができるまで削り続けたといいます。見て覚えなければならない状況に置かれたことで、自主性が芽生え、貪欲に学ぶことができたのでしょう。実力を身に付けるためには、自ら学ぼうとする姿勢を忘れてはいけません。
今日もみんなで「ついてる!ついてる!」